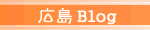「ニッポン異国紀行」(石井光太)読了。
副題は、──在日外国人のカネ・性愛・死。
その通りの内容。いろいろと壮絶だ。
「絶対貧困」「遺体」ほか何冊か読んだけど、この人のルポルタージュは、いいなあ。まなざしが、「問題」にではなく「人間」に届いている。
人間がいる。それなら一緒に生きてみよう、というシンプルな姿勢がいい。
「日本にいる外国人は仲間同士で身を寄せ合うようにして集まり、困った時にはお互いに全力で助け合う。仲間が命を落とした時、病気になったとき、生活に困窮した時、たとえ自分がギリギリの生活をしていたとしても、なけなしのお金を出して仲間を助ける。そうすることで、自分が同じ境遇に陥った際に助けてもらえるようにしているのだ。仲間を救うことは自分を救うことなのである。
きっとそれは外国人同士だけのことにとどまらないのだろう。弱い立場の日本人が外国人を助けることによって自分自身を守ろうとすることもあるのだ。(略)……要はその相手と慰め、励まし合えるかどうかだ。その人間がどこの国の出身だろうとさほど大きな問題ではない。
そう考えると、日本における外国人同士の助け合いは、人間の根源的な生き方なのかもしれないと思うようになった。」
あとがきの最後の文章がまた。
東京の高田の馬場で、朝までタイ人占い師の話を聞いたあとの感想なんだが、「……外国人の多いこの町の空気がとても愛くるしいものに感じられてきた。」
この「愛くるしい」という言葉がすごいわ。おもわず、目があつくなった。
ああ、石原都知事なんかには、絶対言えない言葉だ。
☆
慕わしさ。
いろいろと思い出す。
学生の頃、いや卒業したあとかな、下宿の隣の部屋にやってきた留学生の周さんと、休みの日は一緒にごはんつくって食べたこと。正しくは、彼がつくってくれて私が食べたこと。ネズミにかじられた石けんがたくさんあったので分けてあげたら、それから私をネズミさんって呼んでたけど。経済学のテキストの日本語が難しくて読めないからネズミさん助けてくださいって言われたけど、私も難しくてわかんなくて、ふたりで泣きそうだったこと。
元気かな。またすぐ会えると思っていたのに、互いに行方を見失った。
大学のときの友だちに、バイクにマリリンって名前つけて乗ってた男の子がいたが、彼が、夜の街で、フィリピンの女の子たちが悪いおじさんにからまれてるのを助けてやって、女の子たちと親しくなった。それで彼女たちが店が終わったあと一緒に遊ぼうって、誘われて行った。駅のあたりの川べりで涼んでおしゃべりするだけのことだったけど。女の子は6人いて、同い年くらいだった。そこに立ちんぼのおばさんが通りがかったら、ひとりの女の子が「おかあさん」って駆け寄っていったのが、鮮烈な印象だった。
で、おかあさんは言ったね。「今日は猫にみんなやってしまって、あんたたちにあげるものが何にもないわ」。何か食べるものを買って、それを猫にやりながら客待ちしているんだって。
女の子のひとりは妊娠していて、相手の米兵は彼女を追いかけて岩国にわざわざ転勤してきたんだけど、彼女は別れるつもり、でも子どもは生むつもり。それで彼女は私の友だちのことを好きになってて、それが傍から見ててもわかって、せつなかった。また別の女の子は、お父さんが死んで大学をやめて、弟妹を学校に行かせるために日本に来た。
みんな数ヶ月ごとに各地を転々していた。立ちんぼのおかあさんは、九州から来た人だった。「子どものころは、新聞紙にお弁当つつんでもっていったものよ」って言った。「ここらは、春になったら桜がきれいだから、みんなでお花見しよう」って言ってたけど、春になる前に、女の子たちは次の街へ行ってしまった。
青春という言葉は使えないと思う。私は、あの頃のことを思い出す勇気がない。なんであんなに不安で怯えてて、みじめな気持ちでいたのか。途方にくれて笑ってたのか。思い出したくないけど、
あのみじめさのなかで、周さんや、「おかあさん」やフィリピーナたちと、やさしい時間を過ごした記憶は、どこかで、私が生きることを支えてくれたし、いまも支えてくれていると思う。
そのときは、それから数年後に、フィリピンに行って、ゴミ山を歩いたり、フリースクールの支援に関わったりすることになるなんて、夢にも思わなかったけど。
副題は、──在日外国人のカネ・性愛・死。
その通りの内容。いろいろと壮絶だ。
「絶対貧困」「遺体」ほか何冊か読んだけど、この人のルポルタージュは、いいなあ。まなざしが、「問題」にではなく「人間」に届いている。
人間がいる。それなら一緒に生きてみよう、というシンプルな姿勢がいい。
「日本にいる外国人は仲間同士で身を寄せ合うようにして集まり、困った時にはお互いに全力で助け合う。仲間が命を落とした時、病気になったとき、生活に困窮した時、たとえ自分がギリギリの生活をしていたとしても、なけなしのお金を出して仲間を助ける。そうすることで、自分が同じ境遇に陥った際に助けてもらえるようにしているのだ。仲間を救うことは自分を救うことなのである。
きっとそれは外国人同士だけのことにとどまらないのだろう。弱い立場の日本人が外国人を助けることによって自分自身を守ろうとすることもあるのだ。(略)……要はその相手と慰め、励まし合えるかどうかだ。その人間がどこの国の出身だろうとさほど大きな問題ではない。
そう考えると、日本における外国人同士の助け合いは、人間の根源的な生き方なのかもしれないと思うようになった。」
あとがきの最後の文章がまた。
東京の高田の馬場で、朝までタイ人占い師の話を聞いたあとの感想なんだが、「……外国人の多いこの町の空気がとても愛くるしいものに感じられてきた。」
この「愛くるしい」という言葉がすごいわ。おもわず、目があつくなった。
ああ、石原都知事なんかには、絶対言えない言葉だ。
☆
慕わしさ。
いろいろと思い出す。
学生の頃、いや卒業したあとかな、下宿の隣の部屋にやってきた留学生の周さんと、休みの日は一緒にごはんつくって食べたこと。正しくは、彼がつくってくれて私が食べたこと。ネズミにかじられた石けんがたくさんあったので分けてあげたら、それから私をネズミさんって呼んでたけど。経済学のテキストの日本語が難しくて読めないからネズミさん助けてくださいって言われたけど、私も難しくてわかんなくて、ふたりで泣きそうだったこと。
元気かな。またすぐ会えると思っていたのに、互いに行方を見失った。
大学のときの友だちに、バイクにマリリンって名前つけて乗ってた男の子がいたが、彼が、夜の街で、フィリピンの女の子たちが悪いおじさんにからまれてるのを助けてやって、女の子たちと親しくなった。それで彼女たちが店が終わったあと一緒に遊ぼうって、誘われて行った。駅のあたりの川べりで涼んでおしゃべりするだけのことだったけど。女の子は6人いて、同い年くらいだった。そこに立ちんぼのおばさんが通りがかったら、ひとりの女の子が「おかあさん」って駆け寄っていったのが、鮮烈な印象だった。
で、おかあさんは言ったね。「今日は猫にみんなやってしまって、あんたたちにあげるものが何にもないわ」。何か食べるものを買って、それを猫にやりながら客待ちしているんだって。
女の子のひとりは妊娠していて、相手の米兵は彼女を追いかけて岩国にわざわざ転勤してきたんだけど、彼女は別れるつもり、でも子どもは生むつもり。それで彼女は私の友だちのことを好きになってて、それが傍から見ててもわかって、せつなかった。また別の女の子は、お父さんが死んで大学をやめて、弟妹を学校に行かせるために日本に来た。
みんな数ヶ月ごとに各地を転々していた。立ちんぼのおかあさんは、九州から来た人だった。「子どものころは、新聞紙にお弁当つつんでもっていったものよ」って言った。「ここらは、春になったら桜がきれいだから、みんなでお花見しよう」って言ってたけど、春になる前に、女の子たちは次の街へ行ってしまった。
青春という言葉は使えないと思う。私は、あの頃のことを思い出す勇気がない。なんであんなに不安で怯えてて、みじめな気持ちでいたのか。途方にくれて笑ってたのか。思い出したくないけど、
あのみじめさのなかで、周さんや、「おかあさん」やフィリピーナたちと、やさしい時間を過ごした記憶は、どこかで、私が生きることを支えてくれたし、いまも支えてくれていると思う。
そのときは、それから数年後に、フィリピンに行って、ゴミ山を歩いたり、フリースクールの支援に関わったりすることになるなんて、夢にも思わなかったけど。