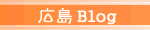思い出したのは、水道を止めた男の話。ついこないだ、本屋で買ったような記憶なのに、奥付を見ると、1987年。もう四半世紀も前だ。
マルグリット・デュラスの「愛と死、そして生活」という本のなかに、水道代が払えなくて、酷暑の夏に、水を止められた一家、夫婦と4歳と1歳の子どもが、鉄道に横たわり一家心中した、という話が出て来る。妻は知的障害があったらしい。彼女は、水道を止める男に何も言わなかった。だって、幼児がいることも、暑いということも、男は見て知っているのだから。男が去ったあと、女は村の顔見知りの居酒屋に行ったが、女は何も語らなかった。水道を止められたことも、これから死ぬということも。
デュラスは、この女の沈黙こそが文学なのだと言っている。その沈黙。
それで私が、その短いエッセイを忘れられずにいるのは、世の中はこんなふうなんだ、ということを、いきなりあざやかに知らされた気がしたからだった。世の中は、知的障害の女の側に立ってはくれないのだ。彼女は沈黙を強いられる。何か言おうとしても、それを聞く耳をもつ人はいないのだ。
世の中は水をとめる男の側にあって、でも彼は、自分の仕事を正しくこなしているだけで、そのために誰かが死においつめられても、そんなことに気づきもしないし、むろん罪に問われることもない。
このエッセイのことをしばしば思い出す。たとえば、電気がとめられた家で、その家の姉と弟がろうそくをつけて、家が火事になったとか、たとえば、母親が発達障害の子どもとの心中をはかったとか、そういうニュースを見ると。
☆
木嶋佳苗被告への死刑判決のニュースで、このエッセイのことをまた思い出した。
何年前か、その事件のニュースを最初に見たとき、そこにあるのは「悪」というよりもむしろ「不幸」であるという気がした。
メディアが見せつけるのは、事件の真相などというものではなく、他人の不幸に群がって戯れる人間の卑しさばかりで、見るにたえない。
私には、彼女の死刑を望む世間が、「水を止める男」に見える。むしろ「悪」は、そちら側にあるように見える。
死刑判決、という。
死ねばいい、と思われたのだ。このひともまた。
朝日新聞読後雑記帳 死刑判決・木嶋佳苗被告の手記を読む
http://
この手記には衝撃を受けた。とても共感する。
昔、学生の頃に、「李珍宇全書簡集」を読んだときの気持ちを思い出す。もう半世紀も前の事件だけど、女子高生を殺害して死刑になった少年の書簡集。犯罪者は、犯罪からも自分自身からも疎外されているのだと、あの本は教えてくれたのでしたが。その疎外から、自分と罪とを救い出す内面の闘いに、私は心ゆさぶられた。
こうしてみると、死刑は、ほんとうに反文化的な制度だ。
「死ねばいい」という声を正当化するばかりの。
「死ねばいい」という声。その声がだんだん大きくなっているみたいで、こわい。その声に、追い詰められて、無実の人だって死ぬだろう。
「死ねばいい」という声に、正義はないとおもう。悪魔は、犯罪者の心のなかにだけ棲むわけじゃない。
死ねばいいと思ったのでしょう あなたには都合の悪いわたしであれば
死ねばいいと思われていても死ぬまでは窓辺に花を飾る女たち
死ねばいいとわたしがわたしに向けていた呪詛の言葉は(要)か(不要)か
死ねばいいと無記名の悪意を浮かべている画面にきみは吸い込まれるな
野樹かずみ『もうひとりのわたしが(略)』
マルグリット・デュラスの「愛と死、そして生活」という本のなかに、水道代が払えなくて、酷暑の夏に、水を止められた一家、夫婦と4歳と1歳の子どもが、鉄道に横たわり一家心中した、という話が出て来る。妻は知的障害があったらしい。彼女は、水道を止める男に何も言わなかった。だって、幼児がいることも、暑いということも、男は見て知っているのだから。男が去ったあと、女は村の顔見知りの居酒屋に行ったが、女は何も語らなかった。水道を止められたことも、これから死ぬということも。
デュラスは、この女の沈黙こそが文学なのだと言っている。その沈黙。
それで私が、その短いエッセイを忘れられずにいるのは、世の中はこんなふうなんだ、ということを、いきなりあざやかに知らされた気がしたからだった。世の中は、知的障害の女の側に立ってはくれないのだ。彼女は沈黙を強いられる。何か言おうとしても、それを聞く耳をもつ人はいないのだ。
世の中は水をとめる男の側にあって、でも彼は、自分の仕事を正しくこなしているだけで、そのために誰かが死においつめられても、そんなことに気づきもしないし、むろん罪に問われることもない。
このエッセイのことをしばしば思い出す。たとえば、電気がとめられた家で、その家の姉と弟がろうそくをつけて、家が火事になったとか、たとえば、母親が発達障害の子どもとの心中をはかったとか、そういうニュースを見ると。
☆
木嶋佳苗被告への死刑判決のニュースで、このエッセイのことをまた思い出した。
何年前か、その事件のニュースを最初に見たとき、そこにあるのは「悪」というよりもむしろ「不幸」であるという気がした。
メディアが見せつけるのは、事件の真相などというものではなく、他人の不幸に群がって戯れる人間の卑しさばかりで、見るにたえない。
私には、彼女の死刑を望む世間が、「水を止める男」に見える。むしろ「悪」は、そちら側にあるように見える。
死刑判決、という。
死ねばいい、と思われたのだ。このひともまた。
朝日新聞読後雑記帳 死刑判決・木嶋佳苗被告の手記を読む
http://
この手記には衝撃を受けた。とても共感する。
昔、学生の頃に、「李珍宇全書簡集」を読んだときの気持ちを思い出す。もう半世紀も前の事件だけど、女子高生を殺害して死刑になった少年の書簡集。犯罪者は、犯罪からも自分自身からも疎外されているのだと、あの本は教えてくれたのでしたが。その疎外から、自分と罪とを救い出す内面の闘いに、私は心ゆさぶられた。
こうしてみると、死刑は、ほんとうに反文化的な制度だ。
「死ねばいい」という声を正当化するばかりの。
「死ねばいい」という声。その声がだんだん大きくなっているみたいで、こわい。その声に、追い詰められて、無実の人だって死ぬだろう。
「死ねばいい」という声に、正義はないとおもう。悪魔は、犯罪者の心のなかにだけ棲むわけじゃない。
死ねばいいと思ったのでしょう あなたには都合の悪いわたしであれば
死ねばいいと思われていても死ぬまでは窓辺に花を飾る女たち
死ねばいいとわたしがわたしに向けていた呪詛の言葉は(要)か(不要)か
死ねばいいと無記名の悪意を浮かべている画面にきみは吸い込まれるな
野樹かずみ『もうひとりのわたしが(略)』